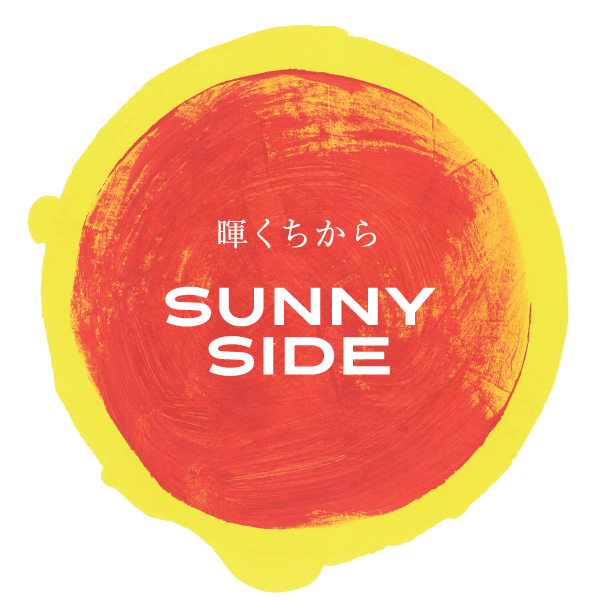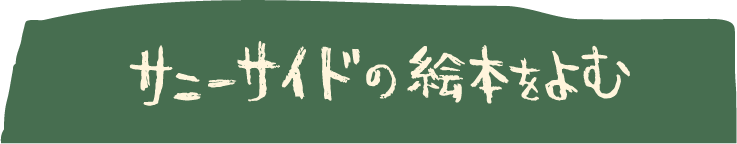恥ずかしがり屋で泣き虫な子ども時代。
僕は恥ずかしがり屋で泣き虫な子どもだった。
両親が土日もなく働く家庭に育ち
社会って怖い、仕事って大変そうだ、と感じていた。
家ではずっとひとりでゲームばかりしていたので
働くことに関心がなく、大人にもなりたくなかった。
だけどなぜか小学5年生のとき、生活委員長に立候補したり、2年生の時点ですら
「ひとりのこらず鉄棒ができるように教えて、丈夫な体にしたい」
という目標を文集に書き残している。
人のことや使命感には燃えるタイプだったのかもしれない。
しかし自分のことだと全くやる気がなく、
近所の高校、そして推薦で行ける大学へと、
無理しなくてもいい進路を選び、大学生になった。
そんなとき、11歳年上の兄が清掃の会社を起業しており
人手が足らず、アルバイトに駆り出された。
清掃の仕事はキツそうだと、友達にもいろいろ言われたけど
バイトもしたことなかった僕は
身近な人や兄弟の「役に立つ」ことにやりがいを感じ
頼られるとなんだかうれしくて、4年間夢中で働いた。