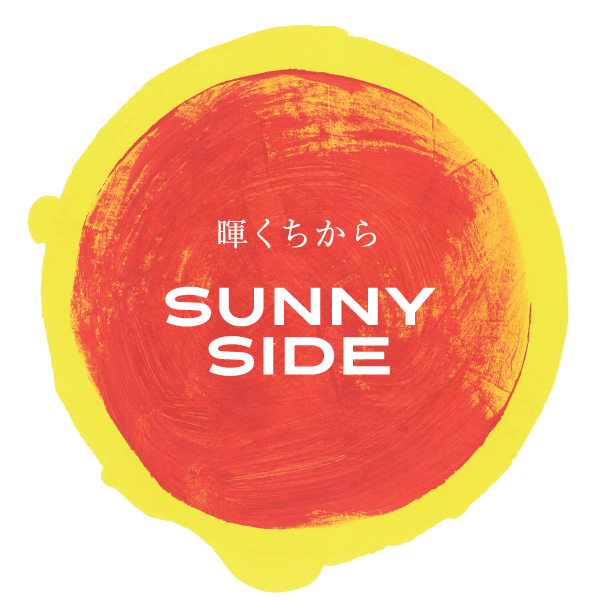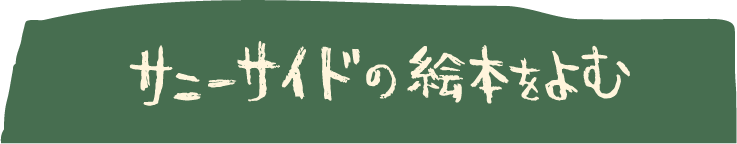八十川さんの日々のお仕事から教えてください。
日々の業務としては、サニーサイドフィールズという施設の運営管理をしています。同時に、ショコラティエというチョコレートを作る仕事をしていて、生産者さんと交流したり、生産者さんだけではなくうちのお店と協力してくださる方とのコミュニケーションを取ったりなど、いろいろなことをしています。
「人を巻き込んでいく」お仕事という感じでしょうか。
いや、巻き込むというのは違います。僕たちのものづくりの考え方なんですけれども、基本的に、主語は「僕たち」じゃないんですよ。
よくあるのは、ものを作りたいから商品を仕入れるという考え方だと思うんです。「おいしいショートケーキを作りたいから、おいしいイチゴが欲しい」とか。そこで自分が主語になっていることにちょっと嫌気がさしていまして(笑)。だって、農家さんがいないと、僕たちはもう、何もできないんですよ。だったらもっと農家さんにフォーカスが当たるべきじゃないかと。
「僕たちが作った美味しいもの」ではなく、「農家さんのことを伝えるためにものづくりをしている」。 ここはチョコレートというものづくりが得意なので、それを生かして「農家さんの作っているおいしいものをお客様に届けて、伝えている」という考え方。ものを作るにあたってはメッセージ性を重視しています。なので、巻き込むのではなく、どんどん巻き込まれたいって感じです。